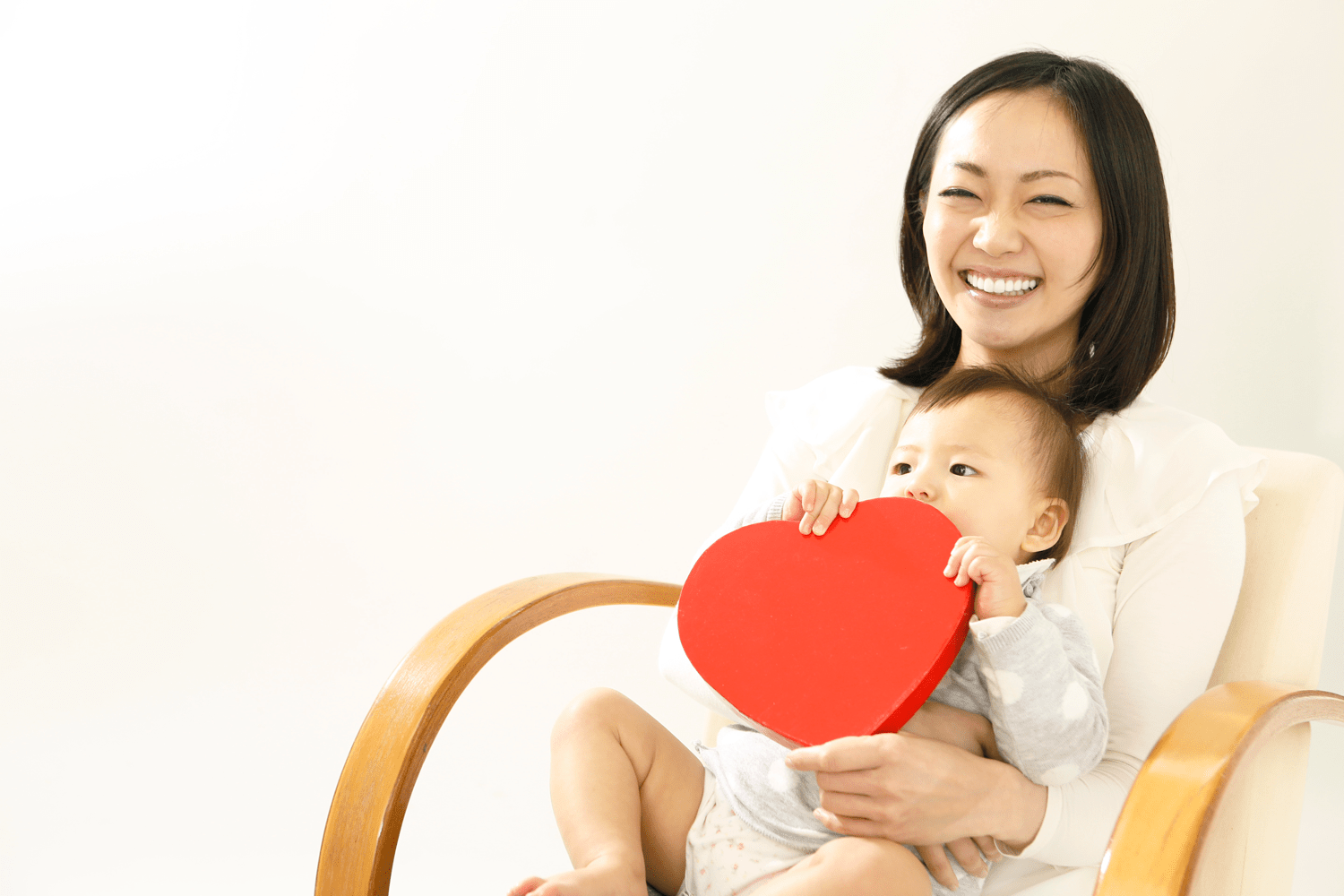今回は、多くの人が悩む「疲れ」や「体力低下」の対策について
疲れのタイプが分かるチェックシートと、タイプ別の「漢方薬」をご紹介します。
疲れチェック1
- 疲れやすい、根気が続かない
- 白髪・抜け毛が増えた、髪がパサつく
- 足腰がだるい・膝や腰に力が入りにくい
- 目が疲れる・目がかすむ・小さな文字が見えにくい
- 耳の聞こえが悪い・聴力が低下した
- 何度もトイレにおきる・キレが悪い・残尿感がある
- つまずきやすい、足がしびれる
- 歯が弱くなった、歯がぐらつく、歯が抜ける
チェック1に当てはまる項目が多い人は
「腎虚/じんきょ=老化」タイプ
老化を予防改善する漢方薬をオススメします。
- 冷え症状がある方→温める生薬がプラスされた八味地黄丸(はちみじおうがん・八味丸)
- 冷え症状がない方→温める生薬を加えていない六味丸(ろくみがん) オススメします。
※腎の働きは30歳頃をピークにそれ以降はどんどん低下し、様々な老化現象が現れます。
老化現象(腎虚)は腎の働きをサポートする漢方を使う事で、加齢に伴う様々な症状を緩和することができます。

疲れチェック2
- 疲れやすい
- 風邪をひきやすい、治りにくい
- 胃腸が弱い、胃もたれ
- 食が細い、食欲がない
- 顔色が悪い(蒼い)
- 声に力がない
- 息切れがする
- 無気力
チェック2に当てはまる項目が多い人は
「脾虚/ひきょ」タイプ
胃腸の働きを良くし気の不足を補う 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)をオススメします。
※気とは目に見えないエネルギーの流れです。
- 気の巡りが滞っている状態を気滞(きたい・気うつ)
- 気が逆流する状態を気逆(きぎゃく)
- 気が不足した状態を気虚(ききょ)
- と言います。 気の不足の気虚の状態になると、気力の低下、元気がない、目や声に力がない、疲労しやすい、めまいや立ちくらみ、食欲不振、下痢などの症状が起きます。

その他に「疲れに効く漢方薬」はこれ
病後の疲れに
- ・黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう)
- 虚弱体質、病後の衰弱、寝汗、湿疹、皮膚炎、皮膚ただれ、腹痛、冷え性の体力虚弱で疲労しやすい方
- ・十全大補湯(じゅうぜんだいほとう)
- 病後、術後の体力低下、倦怠感、食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血がある方
眠れない疲れに
・加味帰脾湯 (かみきひとう)
- 貧血、不眠症、精神不安、神経症の心身の疲れやすい方
胃腸の不調と疲れに
・小建中湯(しょうけんちゅうとう)
胃腸が弱く腹痛があり、血色がすぐれず、体力虚弱で疲れやすい方
・六君子湯(りっくんしとう)
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に。体力中程度以下で、胃腸弱く、食欲が無く、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足の冷えやすい方
暑さによる疲れに
- ・清暑益気湯(せいしょえっきとう)
- 暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏やせ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下に。体力虚弱で疲れやすく食欲不振、ときに口渇ある方
漢方薬と栄養剤・栄養ドリンクの違いは?
漢方薬
漢方薬は証(しょう・お身体の体質や健康の変化)に合わせて選びます。数種類の生薬を処方として配合されたものを漢方薬と言います。証は個人で異なりお身体に合う漢方薬は人それぞれに異なります。
栄養剤・栄養ドリンク
栄養剤・栄養ドリンクは栄養の不足を補う目的で使用します。低価格帯の商品はビタミン類やミネラル類、カフェインが主体です。価格が上がるにつれ中価格帯でアミノ酸製剤,高価格帯で漢方製剤、滋養強壮剤の成分がプラスされていきます。
-
病気による疲労でなければ慢性疲労症候群かも?
まずは原因の有無を検査をしましょう
検査で原因となる病気が見つからなければ→慢性疲労症候群が疑われます。
検査で原因となる病気が見つかれば→その病気を予防治療することで疲労感も解消されます。
慢性疲労症候群症候群とは
慢性疲労症候群症候群は強い倦怠感や疲労と同時に微熱、咽頭痛、関節痛、リンパ節の腫れ、不眠、うつなどの症状が現れます。
慢性疲労症候群をどうすればいいか
- 検査の結果病気がみつからないので、疲労感の決定的な治療法がありません。なので不眠には睡眠薬や睡眠導入剤、うつには抗うつ剤が対処療法としてお薬が処方される場合が多いです。しかし効果的な治療法ではなくあくまでも症状に対する対処です。先ずは漢方薬で体質改善から行っていきませんか?